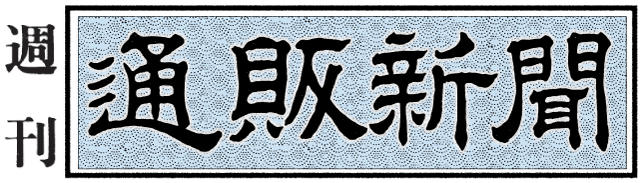新表示制度の「本質」を歪めるな
2015年04月23日 10:01
2015年04月23日 10:01
「機能性表示食品」制度で第一弾となる商品が出そろった。トクホにない機能をうたうものもあり、「企業の自己責任」で運用される制度で、表示の自由度が高まることが期待される。トクホでお馴染みの成分を使う企業もあり、審査を経ない制度の活用で、迅速な商品化も可能になる。ただ、一方で制度の本質を歪めかねない行政の運用に企業の不満の声も聞かれる。「届出制」が、実質的に「許可制」に近い形で運用されていることだ。
制度の根幹は、企業の自己責任による表示だ。安全性や機能性に関する所定の内容を自ら評価して届け出る「事前届出制」が基本。事前届出としたのも販売までの60日間、業界内外の監視に晒されることを前提としたものだ。消費者庁の役割は、届出内容を"形式的"にチェックするにとどまる。
4月の開始からこれまでの届出件数は104件。8商品の受理に要した期間は約2週間だ。消費者庁の板東久美子長官は、受理に時間を要する理由を「(形式的な)修正の依頼、確認のため」と会見で話している。
届出に必要な書類は膨大だ。形式的なチェックで最低限、「書類不備」を確認するだけでも大変な労力であることは想像できる。実際、今回、受理された企業の中にも、評価に影響は及ぼさないが、事後にケアレスミスが発覚したものもある。
ただ、これら受理された企業と同時期にすでに届出を行いながら、いまだ不受理の企業の中には、単なる「書類不備」を超え、「内容不備」に踏み込んだ指摘を受けている節のある企業も複数あるとみられる。機能性表現の内容に関するものだ。
消費者庁が直接、機能性表現を指摘している様子は今のところない。だが、表示内容と科学的根拠のかい離から、"科学的根拠が十分であるか"という視点から確認しているとみられる。遠回しに"その根拠でこの表現は本当に大丈夫か"と、伝えるものだ。消費者庁は「審査でないため表現ぶりを直すことはなく、形式的な確認を行うだけ」とする。だが、確認された企業の中には、表現を指摘されたと感じる企業もある。
これまで例のない新しい制度であるため、消費者庁の慎重な舵取りも理解できる。届出内容が、業界内外のさまざまな識者の目に晒されることを考え、堅い運用で順調な船出を目指しているのだろう。むしろ、「がんが治る」など明らかな違反は明確に指摘するべきでもある。
だが、制度の基本は、あくまで「企業の自己責任」による届出制。水面下の運用では、他社の表現や根拠に対する判断を参考にできず、境界がどこにあるか推察できない。制度に否定的な消費者団体や学識経験者の批判に晒される面があるかもしれないが、そこで揉まれてこそ企業の対応力が高まる。安倍首相は、企業の自己責任による制度で機能性表示を解禁し、中小にも門戸を開くと語った。前例に学べる素地があるからこそ中小が学び、活用企業の幅も広がる。合否判定のように、水面下で受理不受理に一喜一憂する運用ではバランスを欠き、「届出制」は形骸化する。消費者庁は最低限の運用に努めるべきだ。