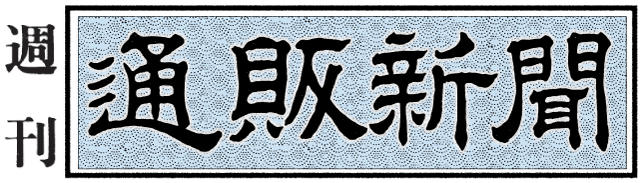再春館製薬所 顧客・社員の"聴こえ"改善、「聴覚」に優しいコールセンター構築へ
2018年09月13日 10:32
2018年09月13日 10:32
再春館製薬所が「聴覚」に優しいコールセンター構築を目指す。会話支援システムの開発・販売を行うユニバーサル・サウンドデザインと、システムの共同開発に向けた業務提携を締結。コミュニケーターの"聴こえ"を改善することで、電話によるコミュニケーションで感じるストレスを軽減する。接客力の向上など顧客との関係強化にもつなげる。
会話支援システム、独自開発へ
グループの再春館システムと3社共同で取り組むもの。今年11月をめどに試作機を自社コールセンターに導入するほか、将来的にグループでコールセンター代行事業を行うヒューマンリレーションへの導入も視野に入れる。
新システムには、ユニバーサル・サウンドデザインが高齢者や難聴者との音声対話支援を目的に開発した独自技術「Sonic Brain(ソニックブレーン)」を活用する。音声情報を高精細化し、脳が認識しやすい音を実現するもの。声のこもりや音の抜けを減らし、クリアな音に変換する。この技術を使いつつ、新たなヘッドセット(マイクとイヤホン)、高波数音域を拾うなど周波数の調整などが行えるアンプも開発する。
ストレス軽減「働き方改革」に
背景には、現状のテレマーケティングが社員の耳や脳への負荷につながっているとの課題認識がある。再春館製薬所は、電話によるコミュニケーションを重視。自社コールセンターでは、社員約1000人が働き、500回線の電話には1日7000件を超える電話が寄せられる。
ただ、現状は通信網やマイクなど機器性能により周波数が限られる。
一般的に、NTT公衆網を通じた音声は、音域が300~3400Hz(ヘルツ)。音質も下がり、例えば「佐藤」と「加藤」など、4000Hz以降の高周波数音域の子音を使った音声を捉えにくい。このことが電話による音声の聴きづらさにつながっている。
加えて、コミュニケーターの多くは、会話をしながら情報入力や顧客情報の検索など複数の作業をこなす。このため、「(顧客の)声が聞き取りにくいことからヘッドフォンを押さえて会話を聞こうとしたり、聴こえづらさから会話の聞き深めができないという心理が働くなどストレスにつながるケースがある」(同社)という。自社調べでも9割近いコミュニケーターが聴こえづらいことによってなんらかのストレスを感じていた。社員がストレスを感じることなく働ける職場環境を整備することで働き方改革につなげる。
インフラ構築外部に提供も
"聴こえ"に起因するストレスは、多くのコールセンターが同様の悩みを抱えているとみられる。再春館製薬所では、インフラ構築を背景に、開発した会話システムを外販していく。
現在、加齢性難聴などに悩む65歳以上のシニア層は、男性で61%、女性で54%に上るとされる。聴こえづらさから人とのコミュニケーションを避けがちになるといった行動にもつながっている。今後、これらシニアのサポートもこれまで以上に強化していく。