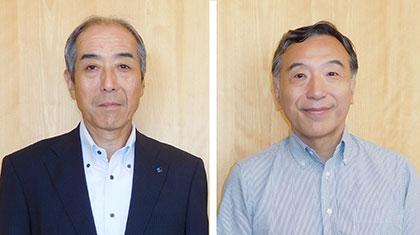 今年度より日本ダイレクトメール協会(JDMA)が、日本メーリングサービス協会(=JMSA)と合流を果たすこととなった。今後は両組織が持つ強みや特徴などを互いに補完しながら、ともにメーリング業界の地位向上に向けた活動をJMSAを舞台に展開していくこととなる。今回、JDMAから新たに役員として参画することになった、添田秀樹副会長(写真左=TOPPANエッジ相談役)と椎名昌彦理事(元JDMA専務理事)に、今後の取り組みについて聞いた。
今年度より日本ダイレクトメール協会(JDMA)が、日本メーリングサービス協会(=JMSA)と合流を果たすこととなった。今後は両組織が持つ強みや特徴などを互いに補完しながら、ともにメーリング業界の地位向上に向けた活動をJMSAを舞台に展開していくこととなる。今回、JDMAから新たに役員として参画することになった、添田秀樹副会長(写真左=TOPPANエッジ相談役)と椎名昌彦理事(元JDMA専務理事)に、今後の取り組みについて聞いた。
――まずは、現在のDM(ダイレクトメール)市場をどう見ているか。 椎名「DM市場として捉えれば、2年連続で前年よりも落ち込んでいる。ただ、市場規模で言えばデリバリーのDMは約3000億円弱で、ここに加えて制作費なども合わせればそれ以上の規模となる。低落傾向とは言え、広告メディアの市場規模としては新聞よりも大きく、まだまだそれなりの存在感がある。
また、トレンドとしては紙や郵便の料金値上げといった逆風がある。共通課題としては、それらのコスト高に業界全体としてどう対応していくかがあるだろう。
今はテレビも含めてアナログメディアが厳しい状況のため、デジタルシフトに対してDMの価値がどこにあるのかを改めて再構築していくことが必要。それはデジタルとアナログの二者択一ということではなく、どう組み合わせるかが大事。これを本当に実践できているところはまだまだ少ないと思う。通販で言えばEC企業はデジタルが主体であり、オールドタイプは印刷メディアしか使っていないのでは。逆に組み合わせができているところは、広告からの流入率で満足度が高いという結果も出ている」
――JDMAでの取り組み実績とは。 椎名「元々、JDMAはDMメディアの振興・活用が中心で、その効果や価値のアピールを行っていた。具体的には消費者向けのDM実態調査などを行い、受け取り通数や開封・閲読率、行動喚起率などを定点観測で調査してきた。デジタルメディアと違ってアナログではこうしたデータがなかったために業界として信用できるものを提示したいということで取り組んでいた」
――調査で得た内容とは。 椎名「例えば、この10年間で見たDMの開封閲読率は平均で7~8割程度あること。また、自分宛てに来たDMに対してサイト閲覧や来店、購入など何らかのアクションをとった行動喚起率は20%あることが分かっている。このリーチ率は広告メディアとしては非常に高いもので、コンバージョンレートとしてもメールマーケティングと比べると2桁くらい高い数値となる。広告の単価としてはメルマガなどのデジタルと比べると高くなるが、費用対効果で見ればデジタルとも十分戦える領域にある。
ここで得たデータを基に、会員企業に対して活用のノウハウを提供したり、認証制度も作って、DMマーケティングのエキスパートやコンサルタントができる人材、クリエイティブに特化したアドバイザーの育成研修などを継続的に行ってきた。ほかにも、日本郵便が開催している『全日本DM大賞』の審査員を務めたり、主要な受賞作品を取り上げて、社会に対してDMの成功事例の共有・発信を図っていた」
――今回の合流の経緯について。 添田「やはり、郵便物の量的減少が大きな要因にある。様々なコミュニケーションツールがSNSなどデジタルツールに変わり、アナログの紙メディアが縮小する中で、そこに携わっている企業も徐々に少なくなってきた。JDMAのコンセプト自体が決して変わったわけでないが、組織運営として変化していくべき時期に差し掛かり、その中でJMSAに合流の検討をして頂いた。元々、両方の協会に加盟している会員も20社程度あった。サービス領域についても互いに得意分野があるため、そこを一気通貫でできるようになるということを感じている」 (つづく)
――まずは、現在のDM(ダイレクトメール)市場をどう見ているか。
椎名「DM市場として捉えれば、2年連続で前年よりも落ち込んでいる。ただ、市場規模で言えばデリバリーのDMは約3000億円弱で、ここに加えて制作費なども合わせればそれ以上の規模となる。低落傾向とは言え、広告メディアの市場規模としては新聞よりも大きく、まだまだそれなりの存在感がある。
また、トレンドとしては紙や郵便の料金値上げといった逆風がある。共通課題としては、それらのコスト高に業界全体としてどう対応していくかがあるだろう。
今はテレビも含めてアナログメディアが厳しい状況のため、デジタルシフトに対してDMの価値がどこにあるのかを改めて再構築していくことが必要。それはデジタルとアナログの二者択一ということではなく、どう組み合わせるかが大事。これを本当に実践できているところはまだまだ少ないと思う。通販で言えばEC企業はデジタルが主体であり、オールドタイプは印刷メディアしか使っていないのでは。逆に組み合わせができているところは、広告からの流入率で満足度が高いという結果も出ている」
――JDMAでの取り組み実績とは。
椎名「元々、JDMAはDMメディアの振興・活用が中心で、その効果や価値のアピールを行っていた。具体的には消費者向けのDM実態調査などを行い、受け取り通数や開封・閲読率、行動喚起率などを定点観測で調査してきた。デジタルメディアと違ってアナログではこうしたデータがなかったために業界として信用できるものを提示したいということで取り組んでいた」
――調査で得た内容とは。
椎名「例えば、この10年間で見たDMの開封閲読率は平均で7~8割程度あること。また、自分宛てに来たDMに対してサイト閲覧や来店、購入など何らかのアクションをとった行動喚起率は20%あることが分かっている。このリーチ率は広告メディアとしては非常に高いもので、コンバージョンレートとしてもメールマーケティングと比べると2桁くらい高い数値となる。広告の単価としてはメルマガなどのデジタルと比べると高くなるが、費用対効果で見ればデジタルとも十分戦える領域にある。
ここで得たデータを基に、会員企業に対して活用のノウハウを提供したり、認証制度も作って、DMマーケティングのエキスパートやコンサルタントができる人材、クリエイティブに特化したアドバイザーの育成研修などを継続的に行ってきた。ほかにも、日本郵便が開催している『全日本DM大賞』の審査員を務めたり、主要な受賞作品を取り上げて、社会に対してDMの成功事例の共有・発信を図っていた」
――今回の合流の経緯について。
添田「やはり、郵便物の量的減少が大きな要因にある。様々なコミュニケーションツールがSNSなどデジタルツールに変わり、アナログの紙メディアが縮小する中で、そこに携わっている企業も徐々に少なくなってきた。JDMAのコンセプト自体が決して変わったわけでないが、組織運営として変化していくべき時期に差し掛かり、その中でJMSAに合流の検討をして頂いた。元々、両方の協会に加盟している会員も20社程度あった。サービス領域についても互いに得意分野があるため、そこを一気通貫でできるようになるということを感じている」 (つづく)