
「押しつけがましい形ではなく楽しく自然にサステナブルな商品を紹介して、作り手をお客様の想いをつなぎ、生活の中に定着していくための手助けをしていきたい」――。通販専門放送局を運営するQVCジャパンを率いる伊藤淳史CEO(=写真)はここ数年、推進を強化するサステナブル(持続可能)施策の意義についてこう話す。
サステナブル施策は近年、様々な事業者が注力する取り組みだが、消費者を置き去りにした独りよがりなものになってしまうことも少なくない。同社ではCR(コーポレート・レスポンシビリティ)の観点から数年前から放送をスタートした自然や動物、環境・生態系を意識した素材やブランド、繰り返し使用できる商品の紹介に特化した番組について再強化を進めて成果も出始めているようだ。
同社は2022年2月から運営する通販専門放送局「QVC」で「未来にいいもの サステナブルな暮らし」と題したサステナブルな商品の紹介に特化した番組をスタート。「廃棄物の削減」など月ごとにテーマを設けてエコバッグや真空断熱技術で長時間の保冷・保温ができる水筒などを紹介。長らく午後7時から1時間にわたって毎週(金曜日)、放送を継続してきた。
「テレビという(伝播性の高い)媒体の特性上、社会生活に与える影響は非常に大きい。企業として商品を販売して利益を上げることは当然だが公の電波をお借りして事業を展開している我々の役割として日本の社会が持続可能であるよう人や地球にやさしい商品を提案することでサステナブルな商品が当たり前となる市場の実現に貢献したい」(伊藤CEO)として開始した同番組で環境意識の高い消費者が増え始めたことで出足は順調だったようだが、徐々に売り上げは減少していったという。
その原因を探ったところ、一因として番組で紹介する商品の「サステナブルさが〝こじつけ〟なもの」となっていたケースがあり、それゆえに顧客に響かず、売り上げに結びつかなくなっていったことがわかったという。「例えば節電つながる家電など。節電はサステナブルであり、かつお客様のお財布にもやさしいと訴求していた。もちろん、その通りなのだが、それらは番組で紹介すべき本当のサステナブル商品なのか。売れるものが優先になってないか。そうした商品は『これは違うでしょう』という反応となり、売り上げも伸びていかなくなった」(同)という。
サステナブルの取り組みと言えども売り上げがついてこなければ継続はできないわけで「一旦、立ち止まろう」(同)と昨年から当該番組の放送頻度を毎週から不定期とした。毎週、サステナブルな商品を紹介しなければいけないという時間的な制約をなくして本当のサステナブル商品を厳選して紹介できるようにした。加えて、「社員のサステナブルに関する知識がそのままでは、従来までの考え方で(商品を)探してしまうことになりかねないし、サステナブルの定義も社員ひとり一人によって異なっている」(伊藤CEO)ことや番組を開始した22年当時から変化したサステナブルの世の中の浸透度なども考慮して、外部の専門家を招いて社員のサステナブルに関する知識レベルの引き上げや新たなサステナブル施策を展開するためのプロジェクト「サステナブル・コマース・プロジェクト(サスコマ)」を実施した。
同取り組みでは当該番組に携わるスタッフを始めとした様々な部署の社員約30人が横断的に参加したサステナブル推進チームが自律的に顧客にサステナブルの価値を届けられるようにすることを目的に昨年6月から9月までの4カ月間にわたって実施。サステナブルに関するコンサルティング会社にサポートを受けつつ、商品の調達など商業部門の業務領域に関連する最新のサステナブルに関する知識をインプットしつつ、具体的なターゲット層をイメージしながら販売すべきサステナブルな商品や実施すべきサステナブルな施策のアイデアの検討、提案などをグループごとのワークショップ形式で実施した。
同取り組みの結果、「サスコマでは最後にサステナブルな商品と体験を組み合わせた商品の展開の提案を参加者から私がプレゼンを受けた。その提案を考える過程の中でサステナブルの定義が整理され、お客様にどのポイントをサステナブルとしてお伝えすればよいかというポイントも整理され、これまで足りなかった生活者視点でサステナブルな商品や企画を考えられるようになった」(伊藤CEO)として、実際に現在は木曜日に不定期に放送する「未来にいいもの サステナブルな暮らし」でも紹介する商品はもちろん、「番組構成や紹介方法が格段によくなった」(同)ことで売り上げも回復傾向にあるよう。
今後も顧客視点での商品選定や訴求を強化していくほか、当該番組以外の番組でもサステナブルな商品の紹介を進める。また、「サスコマ」で企画した体験型の新たなサステナブル商品の販売なども実施していく考えでサステナブルな商品の販売・展開を強化していくという。


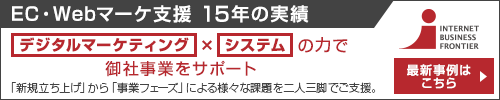

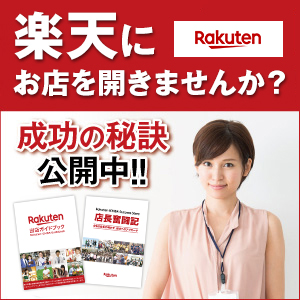
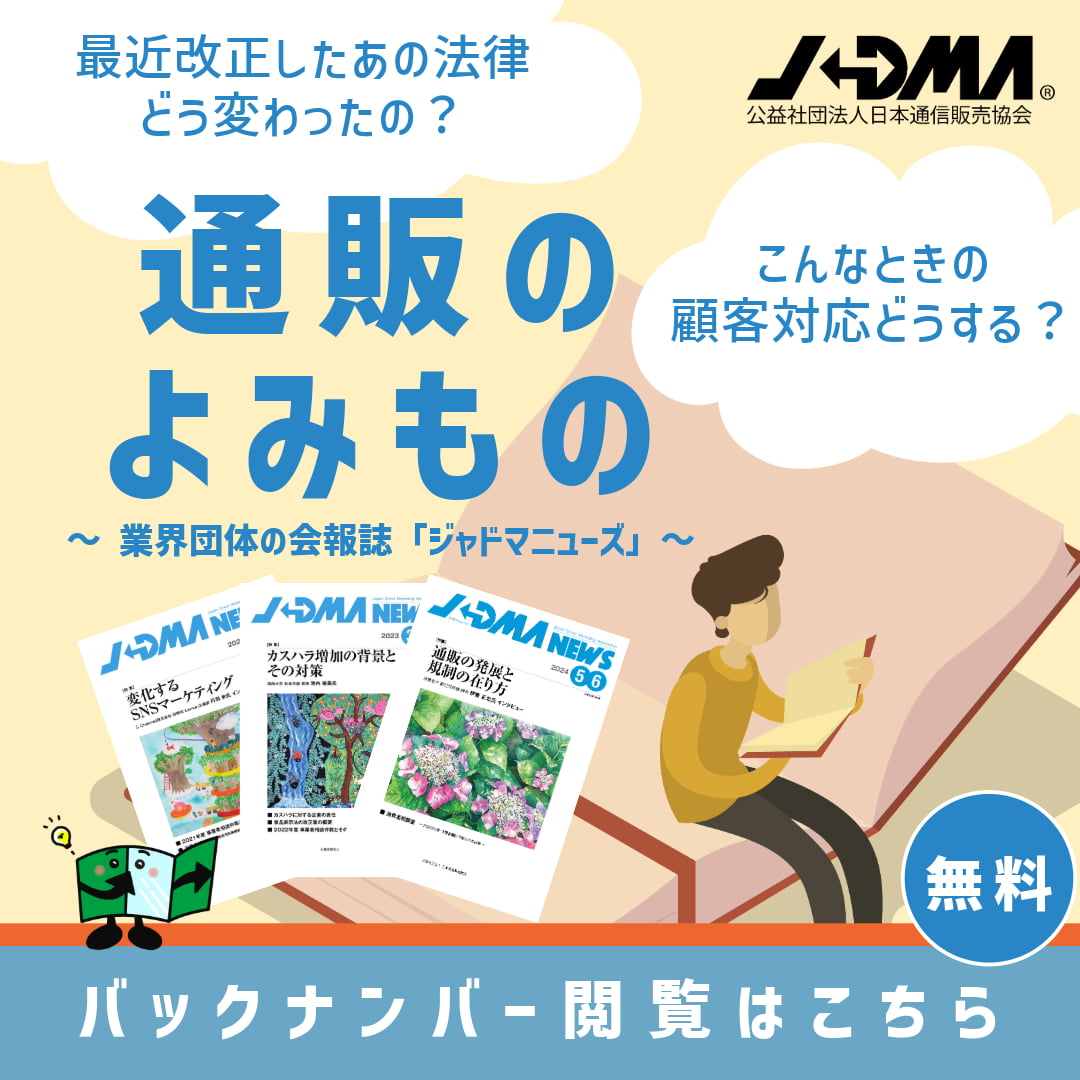





サステナブル施策は近年、様々な事業者が注力する取り組みだが、消費者を置き去りにした独りよがりなものになってしまうことも少なくない。同社ではCR(コーポレート・レスポンシビリティ)の観点から数年前から放送をスタートした自然や動物、環境・生態系を意識した素材やブランド、繰り返し使用できる商品の紹介に特化した番組について再強化を進めて成果も出始めているようだ。
同社は2022年2月から運営する通販専門放送局「QVC」で「未来にいいもの サステナブルな暮らし」と題したサステナブルな商品の紹介に特化した番組をスタート。「廃棄物の削減」など月ごとにテーマを設けてエコバッグや真空断熱技術で長時間の保冷・保温ができる水筒などを紹介。長らく午後7時から1時間にわたって毎週(金曜日)、放送を継続してきた。
「テレビという(伝播性の高い)媒体の特性上、社会生活に与える影響は非常に大きい。企業として商品を販売して利益を上げることは当然だが公の電波をお借りして事業を展開している我々の役割として日本の社会が持続可能であるよう人や地球にやさしい商品を提案することでサステナブルな商品が当たり前となる市場の実現に貢献したい」(伊藤CEO)として開始した同番組で環境意識の高い消費者が増え始めたことで出足は順調だったようだが、徐々に売り上げは減少していったという。
その原因を探ったところ、一因として番組で紹介する商品の「サステナブルさが〝こじつけ〟なもの」となっていたケースがあり、それゆえに顧客に響かず、売り上げに結びつかなくなっていったことがわかったという。「例えば節電つながる家電など。節電はサステナブルであり、かつお客様のお財布にもやさしいと訴求していた。もちろん、その通りなのだが、それらは番組で紹介すべき本当のサステナブル商品なのか。売れるものが優先になってないか。そうした商品は『これは違うでしょう』という反応となり、売り上げも伸びていかなくなった」(同)という。
サステナブルの取り組みと言えども売り上げがついてこなければ継続はできないわけで「一旦、立ち止まろう」(同)と昨年から当該番組の放送頻度を毎週から不定期とした。毎週、サステナブルな商品を紹介しなければいけないという時間的な制約をなくして本当のサステナブル商品を厳選して紹介できるようにした。加えて、「社員のサステナブルに関する知識がそのままでは、従来までの考え方で(商品を)探してしまうことになりかねないし、サステナブルの定義も社員ひとり一人によって異なっている」(伊藤CEO)ことや番組を開始した22年当時から変化したサステナブルの世の中の浸透度なども考慮して、外部の専門家を招いて社員のサステナブルに関する知識レベルの引き上げや新たなサステナブル施策を展開するためのプロジェクト「サステナブル・コマース・プロジェクト(サスコマ)」を実施した。
同取り組みでは当該番組に携わるスタッフを始めとした様々な部署の社員約30人が横断的に参加したサステナブル推進チームが自律的に顧客にサステナブルの価値を届けられるようにすることを目的に昨年6月から9月までの4カ月間にわたって実施。サステナブルに関するコンサルティング会社にサポートを受けつつ、商品の調達など商業部門の業務領域に関連する最新のサステナブルに関する知識をインプットしつつ、具体的なターゲット層をイメージしながら販売すべきサステナブルな商品や実施すべきサステナブルな施策のアイデアの検討、提案などをグループごとのワークショップ形式で実施した。
同取り組みの結果、「サスコマでは最後にサステナブルな商品と体験を組み合わせた商品の展開の提案を参加者から私がプレゼンを受けた。その提案を考える過程の中でサステナブルの定義が整理され、お客様にどのポイントをサステナブルとしてお伝えすればよいかというポイントも整理され、これまで足りなかった生活者視点でサステナブルな商品や企画を考えられるようになった」(伊藤CEO)として、実際に現在は木曜日に不定期に放送する「未来にいいもの サステナブルな暮らし」でも紹介する商品はもちろん、「番組構成や紹介方法が格段によくなった」(同)ことで売り上げも回復傾向にあるよう。
今後も顧客視点での商品選定や訴求を強化していくほか、当該番組以外の番組でもサステナブルな商品の紹介を進める。また、「サスコマ」で企画した体験型の新たなサステナブル商品の販売なども実施していく考えでサステナブルな商品の販売・展開を強化していくという。